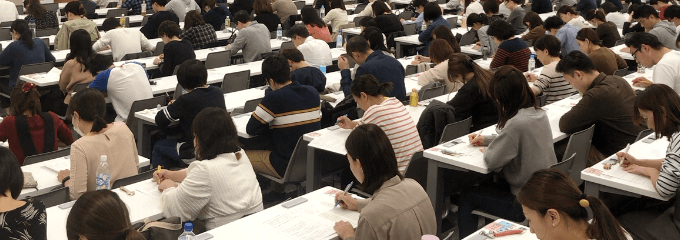りずみんの健康管理コラム
RIZUMIN’S COLUMN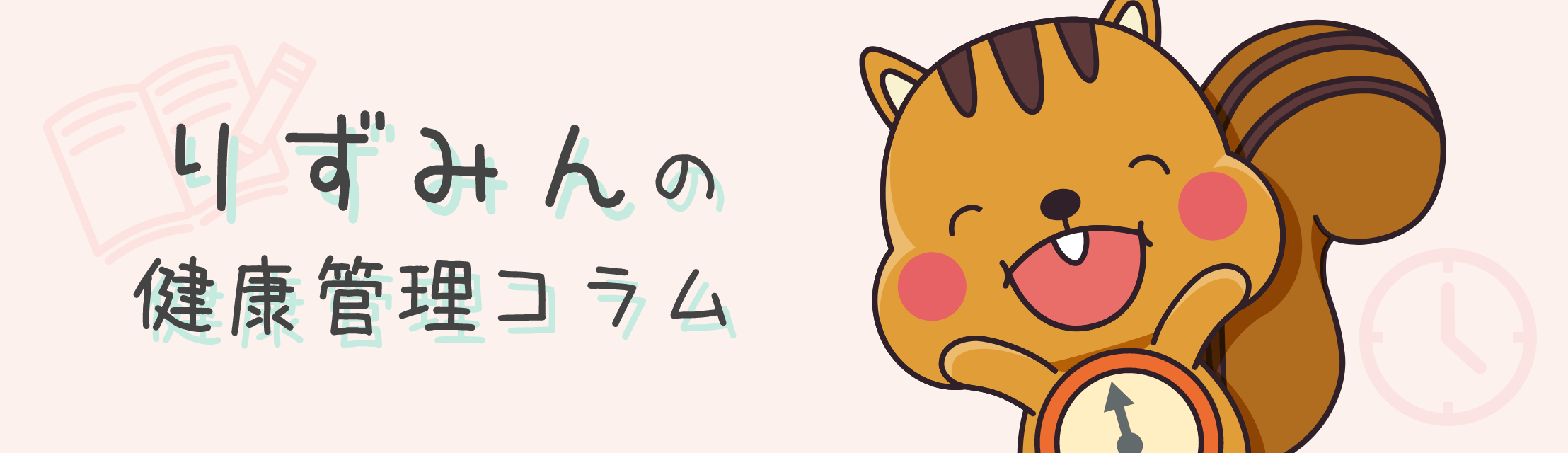
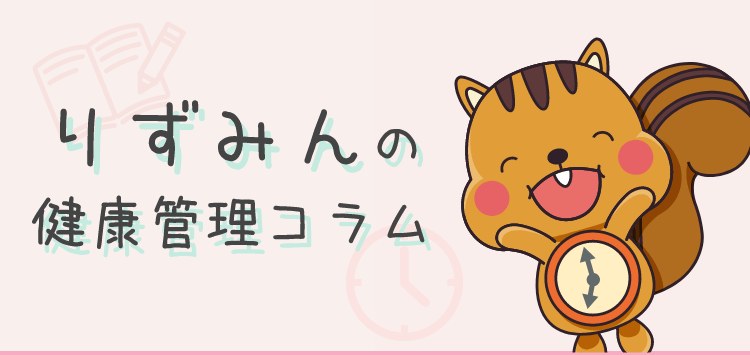
- #季節の変わり目
- #春の健康管理
- #通年
春は運動を始めるのにぴったり!体を動かそう!
5月は、桜が散り新緑が美しい時期です。気温も少しずつ暖かくなり、過ごしやすい日が続いています。そこで、健康的な体を手に入れるために、運動を始めるのはいかがでしょうか。運動は、体にとって様々なメリットをもたらします。
今回は、運動のメリットや種類などについてご紹介します。

運動をするメリット
生活習慣病予防
私たちは、食事から取り入れた糖質や脂肪から体を動かすエネルギーを作り出しています。そのため、食べる量が消費エネルギーを上回ってしまうと、7000kcalごとに1kgの脂肪が蓄積してしまい、糖尿病や脂質異常症、高血圧などの生活習慣病の原因となります。運動を取り入れることで消費エネルギーを増やすことに加え、筋力を増強させることで基礎代謝を上がり、脂肪が燃えやすい体を作ることができます。
精神的な安定をもたらす
春は、日中と夜の寒暖差が激しいだけでなく、精神的なストレスを抱えやすい時期です。運動をすると、ストレスを解消させるためのホルモンであるエンドルフィンが分泌されます。エンドルフィンは、痛みの緩和やリラックス効果をもたらすため、精神的なストレスの緩和に繋がりメンタルの安定をもたらします。
睡眠の質の向上
習慣的な運動は、体内リズムを整えて睡眠の質を高めることがわかっています。運動をすることで、自律神経である交感神経が優位に立ちます。日中にしっかりと交感神経を働かせることで体温が上昇すると、夜に自然と副交感神経が優位に立ち、体温もゆっくり下がっていくため、睡眠モードに切り替えやすくなります。
骨粗しょう症予防
運動習慣がある人は、骨粗しょう症のリスクが低いことがわかっています。特に、高齢者や閉経後の女性は、骨を作る骨芽細胞の働きが弱まり、骨粗しょう症のリスクが高くります。骨は負荷をかけることで、強くなる特性があるため、運動をすることで骨に刺激が加わり、骨芽細胞を活性化させることができます。また、運動だけでなく、十分なカルシウムを摂取することも重要であり、食事も併せて意識することが大切です。
運動の種類
運動とは、身体を動かすこと全般をいい、大きく三つに分類されます。自分のペースで楽しみながら、できる運動を取り入れることが大切です。
ストレッチング
ストレッチングとは、筋肉や関節を伸ばす運動のことで、筋肉の緊張をほぐしたり、体を温めて柔軟性を向上させたりするなどリラクゼーション効果があることが分かっています。運動の前後にストレッチングを行うことで、関節の可動域を高めたり、体を温めることができたりするなど、ケガの予防にも繋がります。

有酸素運動
有酸素運動とは、体内に酸素を取り入れながら糖質や脂肪を燃やし、エネルギーを発生させていく運動です。ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳など長時間継続して続けられることが特徴で、日常生活に取り入れて習慣化させることで、ダイエット効果や持久力の向上に繋がります。
無酸素運動
無酸素運動とは、酸素を使わずに筋肉を使い動かすことで、大きな力を発揮する運動のことです。短距離走、筋力トレーニング、重量挙げなど、一気にパワーを使う運動が挙げられ、継続的に行うことで筋肉量が増加し、基礎代謝量をアップさせることができます。
おすすめは有酸素運動
有酸素運動は長時間低強度の運動を行いますが、この動作は心拍機能を高め、脂肪を燃焼させる効果があります。心臓や肺の働きが強化されることで、体の様々な機能を高めることができます。また、脂肪燃焼効果は、体重減少や維持させるだけでなく、長期間続けることで基礎代謝も上がり、より痩せやすい体になります。
有酸素運動の中でも、始めやすいのがウォーキングです。年齢を問わずに取り入れやすく、道具も必要としないため、いつでも始めることができます。日常で、少し大股で歩いたり、早歩きしたりしてみるだけでも、効果を得ることができます。一日30分程度から取り入れてみましょう。
時間がない人が取り入れるには?
+10分運動をする
仕事などが忙しく、運動に時間を割きにくい人におすすめなのが『+10分運動』です。まとまった運動を行うことは難しくても、ちょっとした工夫をいつもの行動に10分プラスすることで、身体活動を増やすことができます。例えば、一駅分歩いたり、いつもより少し早めに歩いてみたり、買い物に自転車を使わず、歩きで行ったりなどちょっとした意識をすることで、健康効果を得ることができます。

ながら運動をする
ながら運動とは、日常生活の中で何かしらの動作を取り入れて行う運動のことです。例えば、毎日の歯磨き中に足のかかとの上げ下げをしたり、テレビを見ているときは立ち上がって片足立ちをしたりするだけでも健康維持に繋がります。そのほかにも、椅子に座っている時に太ももの内側に力を入れたり、料理をしながら腹筋に力を入れたりなど、それぞれの生活スタイルに合わせて運動を取り入れてみましょう。
食後すぐの運動には注意
食後すぐの運動は、胃や体に負担をかけてしまうため、注意をする必要があります。食後は、消化器が消化吸収を行いますが、運動をすることで消化器の働きを阻害してしまい、胃もたれや腹痛などの原因となります。そのため、食後に運動をする場合は、1時間程度空けてから行うようにしましょう。なお、食事後の運動は、糖質が体脂肪になるのを防いだり、血糖値の上昇を抑えたりするなど体にとって良い影響をもたらします。

いかがでしたか?
日常的な運動は、私たちが健康に過ごしていく上で、とても重要です。
健康管理能力検定3級では、春の養生や体のリズム、朝におすすめの運動法、2級では運動のリズムやストレッチ法についても学んでいただけます。
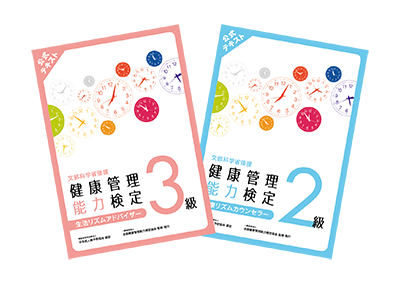
著者: 健康管理能力検定 監修: 日本成人病予防協会