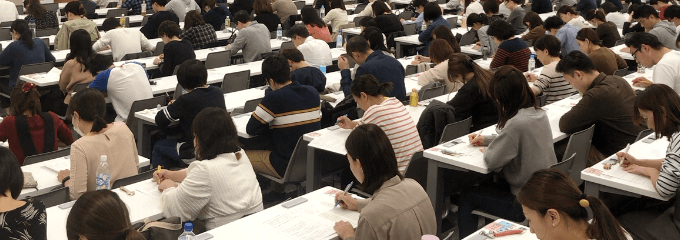りずみんの健康管理コラム
RIZUMIN’S COLUMN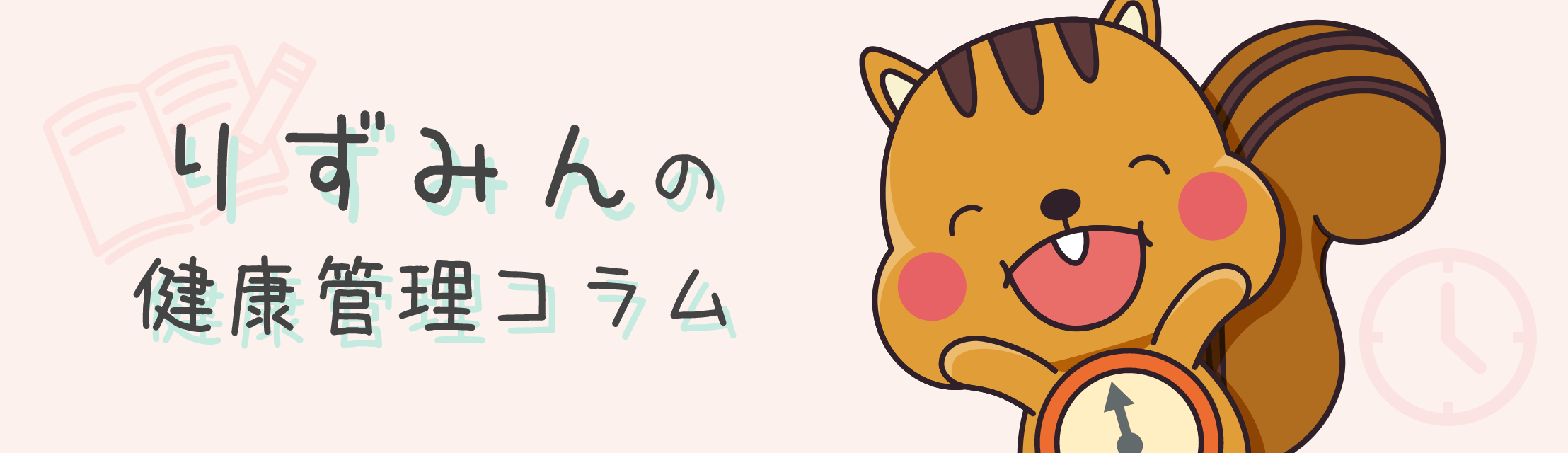
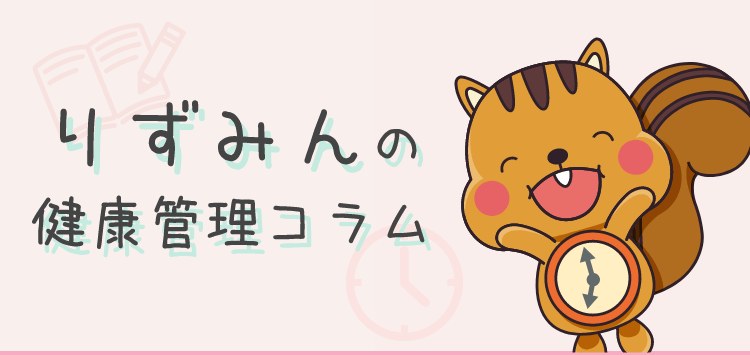
- #秋の健康管理
- #通年
和食月間に朝食を見直そう!
みなさんの朝食は、和食ですか?それとも洋食ですか? 実は、朝食を「和食」にすることで、体のリズムを整えたり、血糖コントロールによい影響があることがわかっています。 11月は「和食月間」であり、11月24日は「和食の日」です。
今回は、和食の魅力を再発見するべく、和食の基本や和朝食のメリットについてご紹介いたします。
和食の日とは
日本は海・山・里といった豊かな自然に恵まれ、米や発酵食品、旬の食材などを活かした「和食文化」が発展してきました。
和食は食卓における自然の美しさの表現や食事と年中行事・人生儀礼との深い結びつきなど、世界に誇るべき食文化として多くの特徴を持っています。
こうした文化を大切にしようと、一般社団法人和食文化国民会議が、11(いい)月24(にほんしょく)日を「和食の日」と制定しました。そこには、一人ひとりが和食文化の認識を深め、大切さを再認識するきっかけの日となっていくよう願いが込められています。
和食の基本「一汁三菜」
和食の基本となる食事構成「一汁三菜」とは、ご飯を主食に、汁物1品、主菜1品、副菜2品を組み合わせた、日本の伝統的な献立の形を指します。この献立により、さまざまな栄養素をバランスよく摂ることができます。
主食
「体に必要なエネルギー源」となる炭水化物を補給します。和食の場合はお米が基本。
三菜
主菜1品、副菜2品で構成。主食を美味しく食べるためのおかずになり、主菜から「体を作るもと」になるたんぱく質、副菜から「体の調子を整える」ビタミン、ミネラル、食物繊維を補給します。
汁物
水分に加え、具材からビタミン、ミネラルなどを補給します。和食の場合は味噌汁が基本。
献立の中で出汁のうま味や発酵食品を活用すると、動物性油脂の摂取量をセーブすることができます。また、さまざまな食材や調理法を取り入れることで、味・香り・彩り・季節感を楽しむことができるのも和食の魅力です。

朝食は和食がいい?
1日のスタートとなる朝食は、活動のエネルギー源となる大切な食事です。また、朝食を摂ることで体と脳をしっかり目覚めさせ、体内時計をリセットしてくれる働きもあります。
朝食の主食はご飯
まず朝食で摂りたいのが炭水化物です。穀類の中でも体内時計をしっかり動かしてくれるのが、ご飯です。小麦を使ったパンでも良いですが、ご飯には食物繊維も含まれており、血糖値の上昇を緩やかにする働きがあります。また、よく噛むことで胃腸の働きが活発になり、体温を上昇させるのにも役立ちます。
魚は朝の理想的なおかず
炭水化物とともに「三大栄養素」といわれるたんぱく質と脂質も欠かせません。そこでおすすめなのが、たんぱく質だけでなく、脂質も同時に摂ることができる「魚」です。
魚に含まれるDHAやEPAには、インスリンの分泌を促し、体内時計を動かす働きがあります。
発酵食品で腸内環境を整えよう
和食の魅力のひとつが、味噌や納豆、漬物などの発酵食品です。これらには乳酸菌や納豆菌など、腸内環境を整える善玉菌が豊富に含まれています。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境が整うことで、免疫機能の向上やストレス耐性の強化にもつながります。
食物繊維で腸内環境を整えよう
朝食で食物繊維を摂ると、朝食後だけでなく昼食後や夕食後の血糖値の急上昇も抑えられることが分かっています。そこでおすすめなのがごぼうや菊芋です。これらには水溶性食物繊維であるイヌリンが多く含まれており、血糖値の上昇を抑えるほか、翌朝の便通を整える働きもあります。
朝食を摂ると、眠っていた胃腸が動き出し、体温や代謝が上がり、脳へのエネルギー供給もスムーズになります。体内時計のリセット効果は昼に近づくほど薄れるため、起きてから一時間以内に摂るようにしましょう。

朝食におすすめのお手軽和食メニュー
ご飯+魚
朝から魚を焼かなくても、ご飯にしらすを合わせたり、コンビニで鮭やツナのおにぎりを選んだりすると、手軽にたんぱく質や魚油を摂ることができます。
調理不要なたんぱく源をプラス
納豆や温泉卵、豆腐、魚肉ソーセージ、かまぼこなどの食材は、切る、加熱するといった調理が不要で、手間のかかる作業をしなくても、手軽にたんぱく質を摂ることができます。
これらの食材やフリーズドライの味噌汁なども活用して、気軽に和朝食を始めてみましょう。
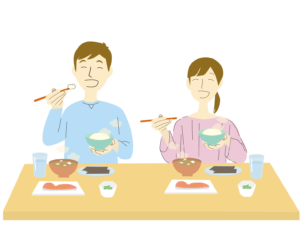
いかがでしたか?
朝は体内時計のスイッチを入れる大切な時間です。
11月は朝食を和食にしてみるのもよいですね。
この機会に、1日の始まりである朝食を見直してみませんか。
健康管理能力検定3級では体内時計の仕組み、朝の過ごし方について、2級では栄養素の働きについても学んでいただけます。
著者: 健康管理能力検定 監修: 日本成人病予防協会