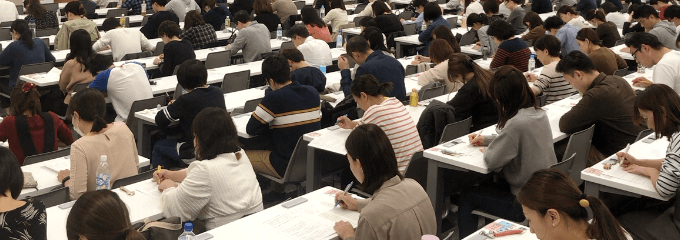りずみんの健康管理コラム
RIZUMIN’S COLUMN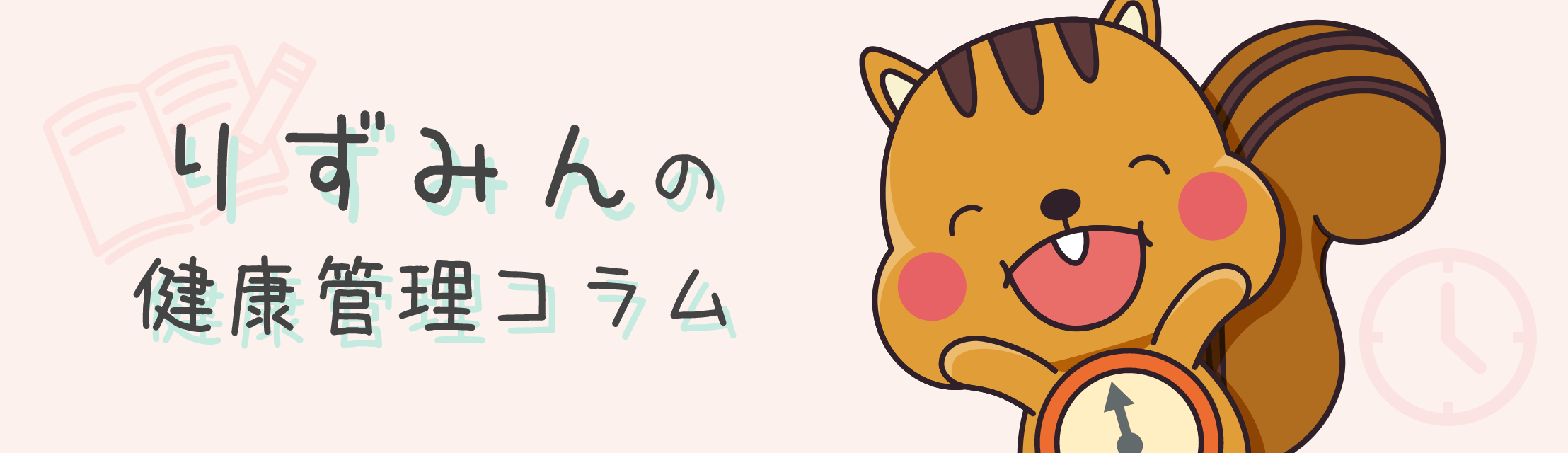
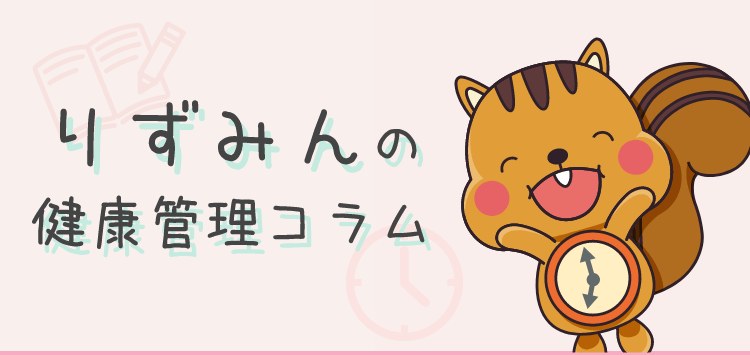
- #季節の変わり目
- #秋の健康管理
秋バテ注意!~寒暖差疲労から体を守る習慣~
10月は「健康協調月間」。職場や地域などの集団単位で「健康づくり」を共通テーマにして取り組む期間であり、心と体の健康を見直す絶好のタイミングです。また、夏から秋にかけての季節の変わり目は、体調を崩しやすく、”なんとなく疲れが抜けない””朝からだるい”といった不調が起こりやすい時期でもあります。
今回は、秋を元気に過ごすためのヒントを、おすすめの3つの習慣とともにご紹介いたします。

秋に増える「なんとなく不調」
春から夏にかけて副交感神経優位になっていた自律神経は、秋から冬にかけて交感神経優位へとシフトしていきます。この変化がスムーズに行われないと、ホルモンのリズムが乱れたり、免疫機能が低下したりして、さまざまな症状が現れます。さらに、この時期は気圧の変動や寒暖差が激しいこともあり、体が気候の変化に適応できず、体調が不安定になりがちです。
寒暖差疲労って何?
朝晩は冷えるのに、昼はまだ暑い。この気温差が引き起こす「寒暖差疲労」をご存知でしょうか。
「寒暖差疲労」とは、気温の変化が原因で生じるさまざまな不調のことをいいます。寒暖差というのは、1日のうちの最高気温・最低気温の差、前日との気温差、1週間単位での気温差、室内外(冷房の効きすぎた部屋やお風呂場)での気温差が当てはまります。
目安ではありますが、気温差が7℃以上になると体温を調整する自律神経に負担がかかり、頭痛、肩こり、めまい、だるさ、イライラ、不眠などの症状が出やすくなります。
寒暖差疲労セルフチェック
次の項目にいくつあてはまりますか?
寒暖差疲労が起きていないかチェックしてみましょう!
□朝起きても疲れが取れていない
□頭痛や肩こりが増えた
□不眠である(寝付きが悪い、眠りが浅いなど)
□手足の冷えやのぼせがある
□気温差に敏感で体調を崩しやすい
□イライラや気分の落ち込みがある
3個以上当てはまると、寒暖差疲労の可能性があります。
※このチェックシートは、体調の変化に早めに気づくための参考としてお使いください。不調が続く場合は、無理をせず医療機関で受診しましょう。
寒暖差疲労を防ぐ3つの習慣
ここからは、寒暖差疲労を防ぐために今日から始められるおすすめの習慣を3つご紹介いたします。
服装で「寒暖差ストレス」をコントロール
気温の変化に柔軟に対応できる服装を心がけることが大切です。
〈朝晩は冷えるので重ね着を〉
気温に応じて脱ぎ着できる服装が理想です。特に通勤・通学時や外出時は、携帯できる羽織り物(カーディガンやウインドブレーカー、ストールなど)が便利です。
〈「首」のつく部分は冷やさない〉
「首」「手首」「足首」は、皮膚のすぐ下に太い血管が通っています。ここが冷えると体温が奪われ、自律神経が乱れやすくなります。マフラーやスカーフ、アームウォーマー、レッグウォーマーなどを活用して、冷たい風が当たらない工夫をしましょう。

入浴で自律神経をリセット
〈入浴の時間〉
夕食後1時間以上経過してからお風呂に入り、寝る1時間位前までにお風呂から上がるというのが、効果的な入浴のタイミングです。理想的なのは、19時頃に夕食を食べて、20時30分頃からお風呂に入り、22時頃に寝るという生活リズムです。お風呂から上がって30分~1時間経過した頃に体温が下がることで、寝つきもよくなります。
〈湯温〉
無理な長風呂や熱過ぎるお湯は、交感神経が優位になるため、38~40℃の少しぬるめのお風呂にゆったりと浸かって、副交感神経を優位にしましょう。
また、炭酸入浴剤を使用した炭酸風呂もおすすめです。皮膚から取り込まれた炭酸ガスにより、末梢血管が拡張して血行が促進されるため、疲労回復に効果的です。さらに、炭酸風呂は交感神経の働きを抑制するという報告もあり、リラックス効果が期待できます。

軽い運動で自律神経を整える
〈リズム運動がオススメ〉
ウォーキングやジョギング、サイクリング、ダンスなど、一定のリズムで筋肉の緊張と弛緩を繰り返す運動を「リズム運動」といいます。
リズム運動は、神経伝達物質であるセロトニンの分泌を活性化させる働きがあり、脳を覚醒させて集中力を高めたり、自律神経のバランスを整えたりする効果が期待できます。特に、日照時間が短くなる秋はセロトニンが不足しやすいため、リズム運動の効果を実感しやすい季節です。
〈朝の散歩で体内時計リセット〉
朝日を浴びながらの散歩は、セロトニンの分泌を促すだけなく、体内時計をリセットする効果もあります。セロトニンは疲れると減ってしまうので、「気持ちがよい、またやりたい」と感じる程度の運動強度がよいでしょう。1日15~30分程度、ゆったりした気持ちで体を動かすことを意識してみましょう。
この時期は晴天の日が多く、気温もほどよく涼しいため、運動には最適の季節です。ただし、小春日和の暖かさには油断しないように注意が必要です。運動や外出時でかいた汗を放置すると、体が冷えてしまい、体調を崩す原因になります。濡れた衣服は早めに着替え、体を冷やさないようしっかり対策しましょう。

体を内側からサポートしよう
寒暖差疲労を防ぐには、自律神経の働きを助ける栄養素をしっかり摂ることも大切です。
以下の栄養素を意識して、体の中から整えていきましょう。
ビタミンB群
エネルギー代謝を助け、神経や筋肉の働きをサポートしてくれます。不足すると疲れがたまりやすく、寒暖差に対する適応力も落ちてしまします。
多く含まれる食品:納豆、玄米、豚肉、たまご、レバーなど
マグネシウム
自律神経の調整や筋肉のけいれん予防にかかわる重要なミネラルです。ストレスや疲れが溜まると消耗しやすく、寒暖差疲労を悪化させる原因になります。
多く含まれる食品:アーモンド、納豆、玄米、ひじきなど
特別なものを用意しなくでも大丈夫です。毎日の食卓に取り入れやすい「納豆」や「玄米」などから、無理なく始めてみましょう。

いかがでしたか?
「なんとなく不調」のサインを見逃さず、生活習慣を整えることが、元気に秋を乗り越えるための第一歩です。今日から始められる「3つの習慣」で、秋の寒暖差に負けない、しなやかで健康な体を育てていきましょう。
健康管理能力検定3級では自律神経やセロトニンの働き、リズム運動について、2級では体内時計の仕組み、栄養素の働きについても学んでいただけます。
著者: 健康管理能力検定 監修: 日本成人病予防協会